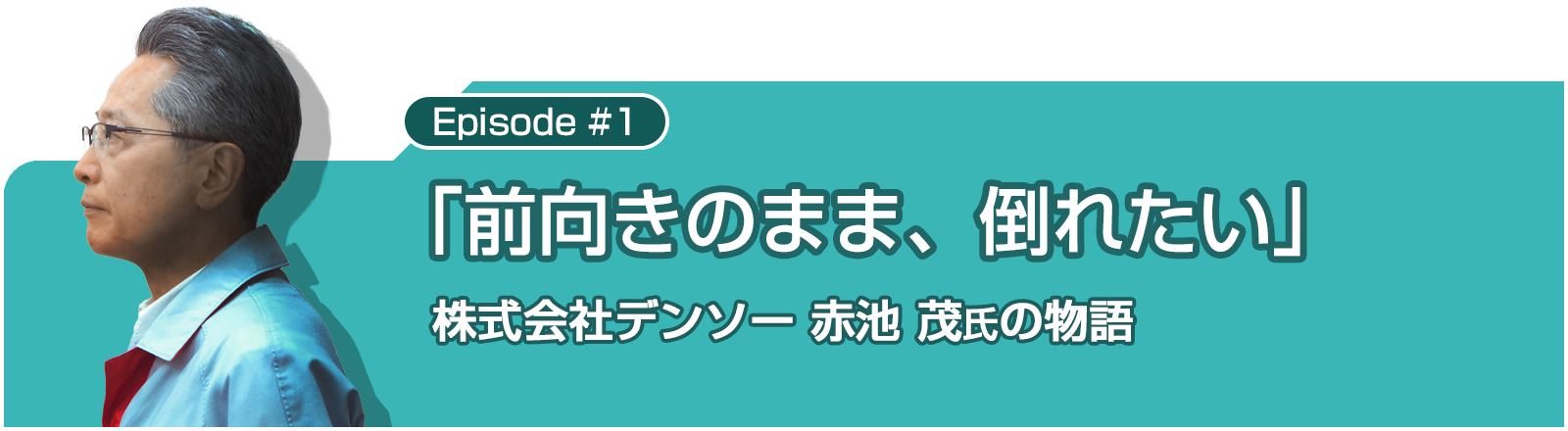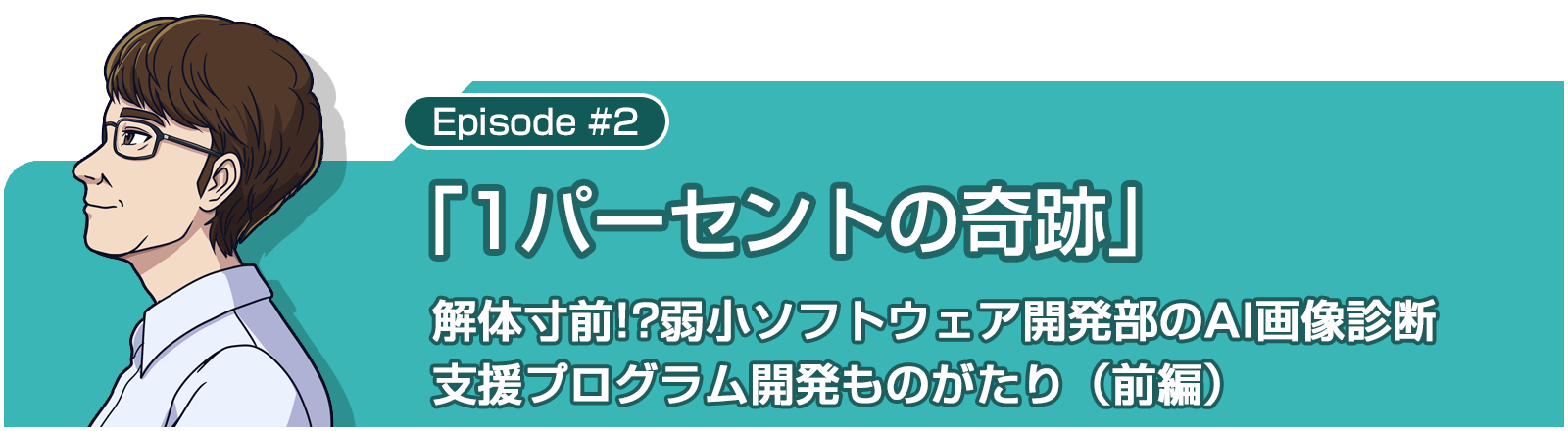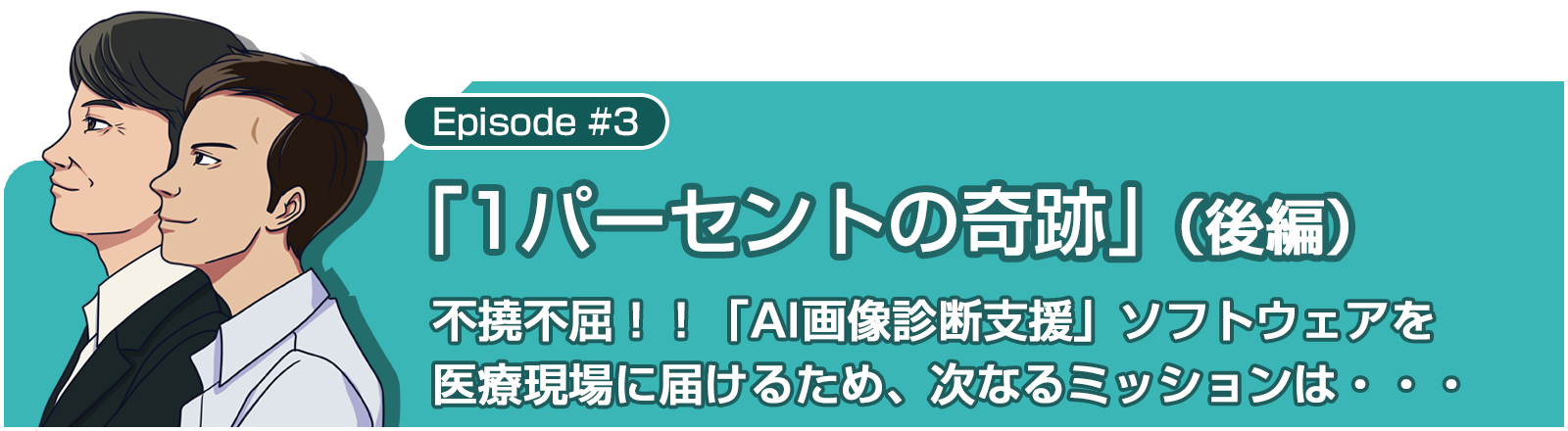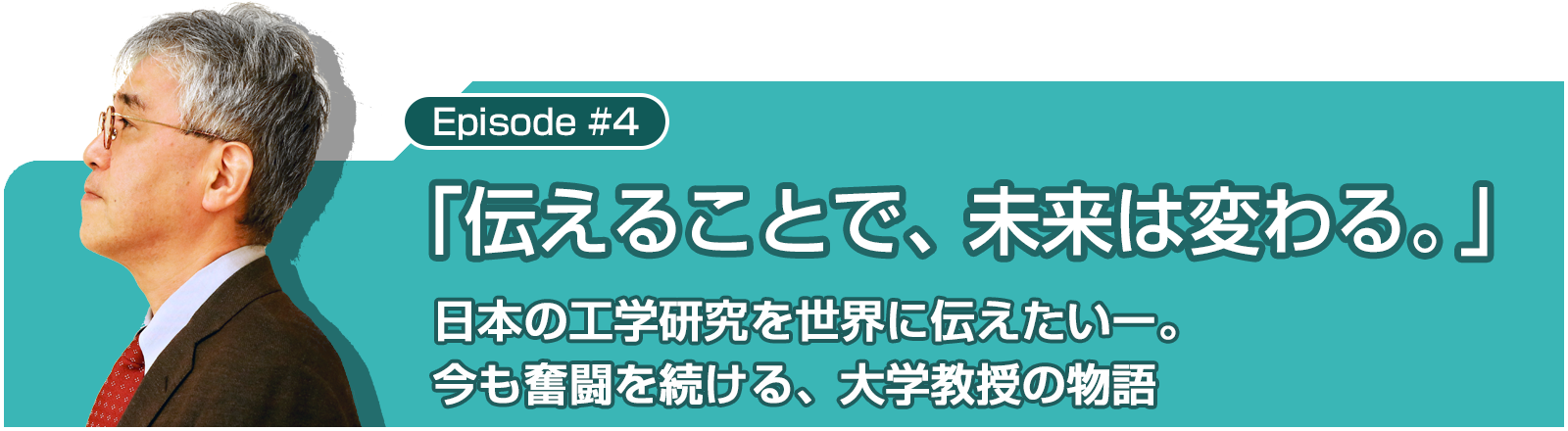|
【プロローグ】 2018年12月、「AIを活用した内視鏡画像診断ソフトウェア」として日本で初めて高度管理医療機器※として承認を受けた「EndoBRAIN」シリーズ。 ※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」 |
AI画像診断ソフト普及の壁
【2020年 春】


「……まいったなぁ…」
医療ソフトウェア開発部の売り上げを眺めていた営業リーダーの久保田がつぶやいた。技術リーダーの河貝は、黙って頷く。
EndoBRAINシリーズが、売れない。
2018年、「AIを活用した内視鏡画像診断ソフトウェア」として大きな期待と共に発売されたEndoBRAINシリーズ。しかし、積極的に導入したいという内視鏡医は多いとは言えない。
理由はいくつか考えられるが、一番は「AIに教えてもらわなくても、自分で診断できる」という、現場の内視鏡医たちの責任とプライドなのかもしれない。AIが診断精度向上に有益だとしても 、世に出たばかりの製品を「なにも自分が一番のりで使う必要はない」と様子見になるのは当然だろう。
そして、EndoBRAIN導入の前に立ちはだかるもう一つの大きな壁は“費用”、すなわち“金”だ。
EndoBRAINは安価な製品ではなく、その投資を回収するのも簡単ではない。EndoBRAINの価値を理解してくれる施設でも、費用面がネックであと一歩を踏み出せないという状況もしばしばあった。
「公的医療保険の診療報酬がついているなら、導入を検討できるのですが。」そんな意見が、医療関係者からはよく聞かれた。
「公的医療保険の診療報酬」とは?
簡単に言うと、診療報酬がついた製品を使って医療行為をした際、公費や社会保険料などの財源から医療機関へ報酬が支払われるようになる仕組みのことだ。厚生労働省(以下、「厚労省」)の専門機関によって厳しく審査された医療機器/医薬品のみ、その対象となる。
診療報酬のつかない医療機器/医薬品は、それを使って医師が患者さんを診断/治療しても、報酬は支払われない。何百万円も払って高い機器を購入しても、医療機関側に金銭的なメリットは少ないのだ。そのため、現在EndoBRAINを導入している施設は、研究志向の強い医療機関や先進的な医療を強みとする大病院に限られていた。
もしEndoBRAINシリーズに診療報酬がつくようになれば、導入が広まる大きなきっかけとなるのは間違いないだろう。
ちなみに2020年4月現在、AIによる診断支援を行う医療機器に診療報酬加算がついた例は、まだ2~3件と非常に少ない。大腸内視鏡用の画像診断という用途に限れば、ゼロだ。
そんなとき、二人の背中を押してくれたのは、昭和大学の三澤先生だった。
「EndoBRAINシリーズの診療報酬加算を申請してみてはどうでしょうか?」
三澤先生は、2018年以前からソフトウェア開発部に長年協力してくれていた昭和大学の研究チームの中心人物だ。昭和大の研究チームは、EndoBRAINシリーズの共同開発者として、国内外の医療機関と協力しながら、着々と検証を進めていた。中でも、内視鏡検査中にAIが病変候補の検出を支援する「EndoBRAIN-EYE」は、その有効性を実証した研究の成果を三澤先生がいくつもの論文で発表しており、すでに国内外の医療系メディアに掲載されていた。
これらの成果があれば、診療報酬加算の申請に非常に有利になることは間違いない。
とは言っても、前例も少ないAI医療機器への加算には厚労省も慎重だろうし、簡単でないのは目に見えている。そもそも、慢性的に人手不足のうちの部に、そんなことができるのだろうか。
悩んでいる暇はない。診療報酬の見直しは2年に1回しか行われないため、決断を急ぐ必要もあった。
仕事帰りの久保田と河貝は、どちらから誘うでもなく、2人で行きつけの餃子屋に足繁く通っていた。この店の開放的な雰囲気と大ぶりの焼き餃子は、本音で議論しやすい環境を提供してくれる。
「……できるかどうかじゃなくて、やらなくちゃいけない気がします。」
河貝が言った。
「三澤先生の論文からも分かるように、EndoBRAINには、人々を大腸がんから救える力がある。でも、どんなに良いものを作っても、使われなければ意味がないと思うんです!」
「その通りだと思います。作ったものを普及させていくのも、私たちの仕事ですからね。」
久保田も頷く。
河貝は、かつてEndoBRAINの薬事申請を決意したときのことを思い出していた。

映画『ミッション:インポッシブル』を偶然見て、自分もまた「不可能なミッションに挑戦しよう」と決意し、チームを作ると決意したことを。
「まずは、「やる」と決めよう。」
諦めない限り、可能性は常にある。やり方は……きっと進むうちに見えてくるだろう。
二人は、前向きな気持ちで追加のビールを注文し、乾杯を交わした。
前代未聞の計画、始動!
【2022年 1月】
開発したばかりの新製品「EndoBRAIN-X」と、すでに臨床的なエビデンスも十分な自信作「EndoBRAIN-EYE」について、診療報酬加算(以下、「加算」)を目指す計画が遂に始動した。
新製品のEndoBRAIN-Xについては通常の加算申請を、既存製品のEndoBRAIN-EYEに関しては「チャレンジ申請」を試みる。
同時期に2種類の加算申請に挑むというのは、おそらく前代未聞の計画だろう。
チャレンジ申請とは、加算のない(あるいは少ない)医療機器/医薬品などに対して使用実績や新たな研究成果を踏まえ、診療報酬の金額を見直すための再検討をしてもらえる制度だ。2018年度に導入されたばかりの新制度ということもあり、特にソフトウェア医療機器の申請については、ほとんど情報がない。
とりあえず分かっているのは「チャレンジ権の獲得から手続きを始める」ということ、そして、チャレンジ権取得後に、改めて加算申請のための再審査が必要ということだけだった。
「傍から見ると暴挙だろうな。」まさに五里霧中というこの状況に、自分が決めたこととは言え河貝は苦笑いした。
河貝と久保田がまず始めたのは、この暴挙に挑戦してくれる人材の獲得だ。久保田は申請の主担当に、営業職として2年前に新卒入社したばかりの花井を抜擢した。

花井の情報収集力と分析力は取引先からも高く評価されており、粘り強さや向上心といった、今回のプロジェクトに不可欠な素質も兼ね備えていると考えたのだ。
「花井さんは、大学院で医学分野の研究をしていましたよね?花井さんの知識と経験は、大きな武器になると思うんですけど。」
久保田は花井に尋ねた。
「はい。神経科学の研究をしていました。私で良ければご協力します!」
「これから始めようとしていることは、はっきり言って前代未聞のプロジェクトです。」
「はい!難しいことは分かっていますが……だからこそ挑戦したいんです。精一杯頑張ります!」
担当を引き受けた花井は、積極的に保険申請のセミナーを受講したり、貪欲に厚労省の担当者に質問を繰り返したりしながら、着々と申請業務の知識を蓄えていった。

この頃、医療チームの新リーダーとして渡瀬が赴任してきた。彼は、温厚そうな笑顔とは裏腹に、新規事業をいくつも立ち上げてきた猛者でもある。加算の申請についても理解が早く、困難な状況でもこのプロジェクトを進めることを承認してくれた。
新チーム結成!
【2023年 1月】
「……しんどい。」
オンライン会議を終えたパソコンの前で、花井は思わずつぶやく。
診療報酬申請の担当者になって約1年。
約20ページにおよぶ申請書類のドラフトは提出できたものの、厚労省から来る修正依頼の嵐は、まだまだ収まっていなかった。 今回の申請は社内でも初めての試みであり、過去の資料もなければ質問できる経験者もいない。 とにかく自分で調べ、 厚労省へメールと電話で疑問をぶつけ、難解な英語論文を参考文献として根気強く読み続ける生活が続く。
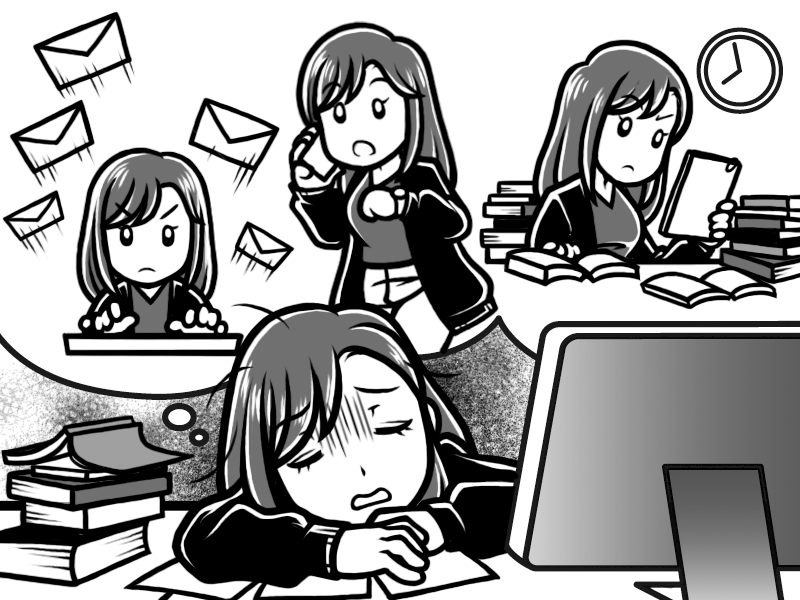
ここまで全力で取り組んできた一番の理由は、「やりがい」に他ならない。まだ入社3年目にもかかわらず大きな裁量を持って申請書類の作成を進め、この分野の第一人者である三澤先生と直接やりとりできることは、他では得難い貴重な経験であった。また、厚労省の担当者の親切丁寧な対応も、大きな励みになっていた。
「でもやっぱり、しんどい……結局は、一人で進めるしかない、孤独な作業なんだよねー…」
終わりの見えない作業量と暗中模索の日々に、花井は気持ちがすり減っていくのを感じていた。
事業部長である渡瀬は、このプロジェクトの重要性を理解していたこともあり、なんとか花井の負担を減らしたいと考えていた。ちょうど、社内全体で人材募集に力を入れていた頃で、彼が部門長を兼任していた他部署にも入社内定が出た人材が何名かいた。その中で、来月入社予定の一人の職務経歴が、渡瀬の目に留まった。
「来月、他の部署に入社予定の小野くんという人がいるんだけど、うちの部に加わってもらうのはどうかな?医療関係の知見はないけど、前職ではAIの開発経験があるんだ。」

EndoBRAINはAI医療機器のため、審査ではAIのプログラムの説明が必要である。花井にはない技術的なスキルを補えるだけでなく、孤独に作業を進めていた彼女に仲間ができることになる。チーム全員が諸手を挙げて賛成し、渡瀬はすぐに動いた。
「小野くん、医療の部署に来たら、絶対に他では得られない体験ができるしキャリアアップにもなる。きっと楽しいよ!」
無事に小野を口説き落としたあとは、元々入社予定だった部署も説得に成功。小野は、無事医療ソフトウェア開発部に仲間入りした。
その頃、河貝も仲間を増やす活動を進めていた。
加算申請がスタートした頃、ソフトウェア開発部の業務に欠かせない薬事担当者が転職してしまい、後任を探していたのだ。
専門的な業務内容ということもあって後任者はなかなか見つからない。
現在は開発担当のエンジニアたちが薬事の業務を兼任していたが、部内の大きな負担となっており、対策は急務だった。
「ちょっと会ってほしい人がいるんだけど。」あるとき、人事部の社員が河貝に声をかけた。
「以前、製品出荷を担当してくれた越山さんっていう人が、産休・育休後に復帰するんですって。すごく評価が高くて他からも声がかかってるんだけど、復職後の所属先はまだ融通が利くみたいなんです。河貝さんのところでどう?」
「そうなんですね。名前は存じていますが、薬事は未経験ですよね?どんな方なんでしょうか?」
「とにかく優秀。どんな仕事も早くて丁寧だし、周りのことをよく見て先回りして動いてくれるって。今風でいうと、圧倒的なシゴデキ?」
「……シゴデキ?」
その前評判に若干緊張が走ったが、河貝はすぐ面接をお願いした。

面接に現れた越山は、どちらかというとおとなしい雰囲気の女性だった。若干拍子抜けしながら話を進めると、控えめながらも的を射た会話のやりとりに、すぐ好感を持った。口数は少なく、自己アピールが強いわけでもなかったが、やる気と情熱も感じられた。
何より印象に残ったのが、話し始めるとキラキラと輝く瞳だ。漫画ならともかく、実際に目がキラキラと輝いている人に出会うことは少ない。ましてや、日々のタスクに追われる現代の大人たちに。
河貝自身が関わってきた人の中にも、こんな目をしている人たちがいることを思い出す。ともにEndoBRAINを開発した、昭和大学の工藤教授、三澤先生、同志の久保田……。
薬事に関してはまったくの素人の越山だが、今この部署にいてほしい人だ。河貝は、自分の直感を信じることにした。
2023年春、越山は医療ソフトウェア開発部に仲間入りした。
「確実に、強いチームができている。」
河貝は、手ごたえを感じていた。あとは後悔しないようにやるだけである。
未来へ託すバトン
【2023年 4月】
花井が苦労に苦労を重ねて提出したチャレンジ申請の書類は、厚労省の審査を経て受理され、EndoBRAIN-EYEは、無事、加算申請の「チャレンジ権」を獲得する。
ようやく加算申請の第一歩を踏み出せた段階であり、まだまだゴールには程遠い。しかし、医療ソフトウェア開発部の喜びはひとしおだった。 なぜなら、今後の審査にはちょっぴり自信があったからだ。 我々には、「EndoBRAIN-EYEを使うと腫瘍の検出率が向上する」というデータがある。
花井も、これまでの苦労が報われた気持ちでいっぱいだった。
「花井さんなら、このまま加算の認可を獲得してくれる!」
医療チームのメンバーも期待を膨らませていたところだった。
しかし、そんなときに限って、思いがけないことが起こるものだ。
花井が、自身のおめでたをチームに告げたのは、チャレンジ権を獲得する少し前だった。ここまでの作業は、体調の変化やつわりの辛さに耐えながらもやってきたことだった。しかし、そろそろ誰かに引き継ぎをしなければならない時期に差し掛かっている。
花井は、後任には迷わず小野を推薦した。

「小野さん、医療の知識も保険の知識もないのに、この大変なときにチームに入ってくれてありがとうございます。ここからさらに厳しい審査もあるけど、小野さんなら絶対大丈夫だと私は勝手に思っています。」
「正直に言うと、不安だらけです……でも、花井さんが作ってくれた完璧な引継ぎ資料のおかげで、これまでの流れや必要情報はかなりつかめてきました。きっと加算が認められると思っています。」
「吉報を待ってますね!」
その年の夏、ギリギリまで申請業務に携わった後、花井は産前産後休暇のため離職した。
<後編につづく>
著 三浦有為子
お読みになられた感想を
ぜひお聞かせください。
アンケートページへ -

医療従事者向けソフトウェア(AI・可視化)
本作に登場する「AIによる内視鏡画像診断支援プログラム」など、AIおよび可視化技術を活用した医療従事者の方向けのソフトウェアを紹介しています。
-

大腸内視鏡診断支援AI「EndoBRAIN-EYE®」が診療報酬の加算対象に
内視鏡画像診断支援プログラム「EndoBRAIN-EYE」が、2024年6月より診療報酬の加算対象となることを告示したニュースリリースです。
-

大腸がんの早期発見へ:国内初、大腸向けAI医療機器が保険診療の加算対象となるまで
「EndoBRAIN-EYE」が、大腸向けのプログラム医療機器として国内で初めて医療保険診療の加算対象となるまでの開発裏話です。